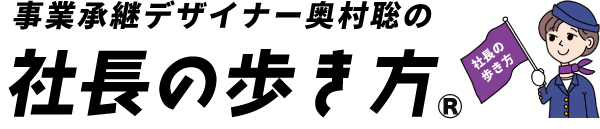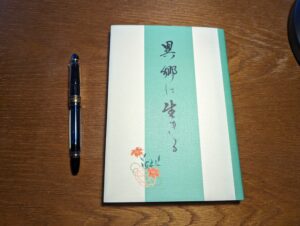廃業、および清算とは?
廃業、倒産、清算・・・と似たような言葉がいくつかあります。
このサイトでは『廃業』を
「自らの意思で自主的に会社や事業をたたむこと」と、
定義します。
会社を続けたいけれど借金などの問題で会社を潰されてしまう
『倒産』と対になる概念です。
ちなみに『清算』は、廃業を決定し、
財産の処分や債務の支払いなどを行って会社を
整理する取組みのことです。
廃業を決定したところで、その場ですぐに会社が無くなるわけではなく、
そこから会社を無くすための清算作業が必要となるのです。
ある後継者がいない会社があったとします。
そのままではいつか会社は潰れてしまうことになるでしょう。
寿命などの時間的制限があるためです。
社長の死亡等により会社が機能不全となり、
急な出来事のために現場や関係者が混乱し・・・
そのとき個客や取引先、従業員、さらには家族が
迷惑を被ったり苦労させられることになるでしょう。
そんな未来予想に対し
「ならば、前もって自分の手で会社や事業を整理しよう」
そう判断して実行することが『廃業』です。
それ以外の動機としては、ご自身の年齢や健康的問題の発生、
未来の経営環境の暗さや業績の悪化などもあり得るでしょう。
ときに後継者の不在が、その判断の一番の決め手となるのかもしれません。
もちろんこれまで続いてきたものが無くなってしまうことは惜しいものです。
しかし、何の手も打たないまま問題を大きくしてしまい、
最後は被害者を増やしてしまうケースと比較すれば、
ずっとましな結末なのかもしれません。
後者のような結末となってしまう会社も多いものです。
廃業の判断材料
どうなったら廃業したほうがいいのか?
また、そのタイミングは?
ほとんどの人にとって初めての体験であるため、
判断は難しいものでしょう。
決断できないままズルズルといきがちです。
ここでは廃業の決断の基準などを考えてみましょう。
➢判断は早めに
この手の重たい話はどうしても後手にまわりがちです。
健康状態の悪化や経済的行き詰まりで、
切羽詰まって廃業するケースも多々あります。
しかし、それでは不利益を
受け入れざるを得なくなる場合が多いでしょう。
判断を早めて先回るスタンスが求められます。
判断を早くすれば、
その後の清算処理などに時間的余裕ができます。
結果的に、手元に残せる資金が増えたり、
節税の取り組みたできたりするのです。
➢廃業のルールを決めておく
早めに判断といっても基準があいまいです。
そこで、あらかじめ『自分の撤退ルール』を
作っておくことをお勧めします。
《撤退ルールの例》
✓2期赤字が続いたら廃業する
✓借金が2000万円を超えそうだったら廃業
✓社長の年齢が68歳になったら廃業
➢清算価値をモニタリングしておく
「廃業したとき、
いくらお金(または借金)が残りますか?」
こんな質問をされてすぐに答えられる社長は
どれほどいらっしゃるでしょうか。
上手に着地したいならば、
頭の中でシミュレーションできていなければいけません。
廃業時のシミュレーションは貸借対照表でできます。
資産から負債を引けばいいのです。
しかし、貸借対照表と現実のそれは、
数字が合っていない場合があります。
資産を現在価値で評価しなおしたり、
決算書に載っていない負債を計上したり・・・
このような調整を行った後に残るものは、現金か借金か?
そして、いくらぐらいでしょうか?
➢もう一度継ぎ手を探す
本当に廃業しか道はないのでしょうか?
廃業が原則と言いながら
やや矛盾しているかもしれません。
ただ事業継承や会社再生の現場にいると
「もったいない」と思う廃業を
目にすることがあるのです。
「声をかけてもらえたら事業の継ぎ手や、
資産の買い手を探せたのに」と
残念な気持ちになることも・・・。
「うちは廃業しかない」と、
はなからあきらめてしまっているケースが多い様子。
しかし、案外事業を引き継ぎたいというニーズはあるし、
会社丸ごとではなくても、資産やノウハウ、
従業員などが求められることは多々あります。
(丸ごと引き継がない方法は、こちらの記事を)
できるだけそのまま引き継いでもらえたほうが、
高く換価できますし、
これまで築いてきた価値を残せたという
気持ちの良さにもつながるはずです。
終わらせるのは簡単ですが、
その前に継いでくれる人はいないか
探してみていただきたいところです。
「死ぬまで現役主義」の社長さんへ
仕事が生きがいという社長も多いでしょう。
生きている限り仕事をしようとする意欲は立派です。
ただ、それとなんの準備もしないことは
意味が違うと思います。
現役を続けるにしても
しておいた方がよい準備はあるはずです。
たとえば徐々に自分ができる範囲の仕事に絞りながら
会社を小さくしていくことも準備の一例です。
また、社長にもしもがあった時に、
会社の廃業を代わりに手掛けてくれる人を
見つけておくこと等もしておいた方がいい場合も多いはずです。
私もこんな約束をしているお客さんがありますが、
家族などに迷惑をかけないで済む準備になるでしょう。